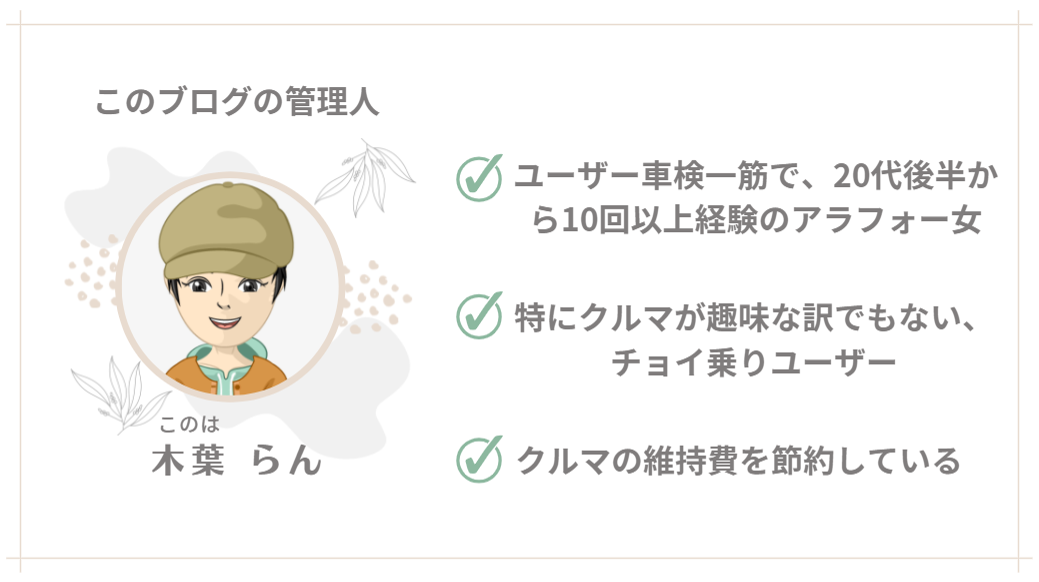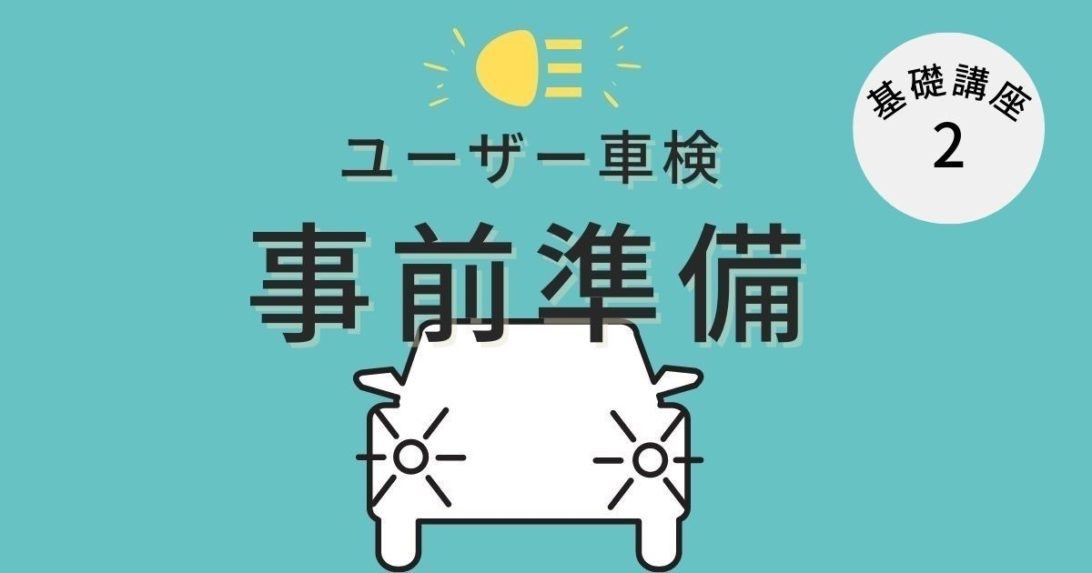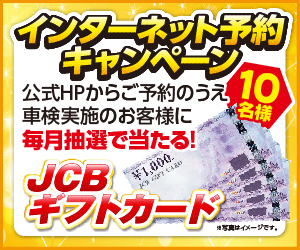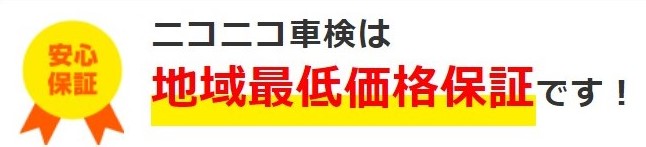これまでユーザー車検を10回ほど受けた経験のある、アラフォー女の木葉らんです。

縁石に乗り上げてタイヤがパンク!なんて経験ありませんか?
こんな経験は滅多にあることではありませんが、はじめての場合はパニックになってしまいますよね。

運転免許を取りたての頃に、カーブ付近で縁石に乗り上げたことがあります。
大したことはなかったので自力で何とかなりましたけど・・・怖かったです。

経験がないので、もし路上で縁石に乗り上げたりタイヤがパンクしたら、どうしたらいいのか分かりません。
実は最近、私の高齢の父親がやってしまったので、その時のことを体験談にしてみました。
幸い誰もケガすることなくてよかったのですが、ただクルマが縁石にはまり込んでしまって動かせなくなってしまいました。
現場に来てくれたロードサービスの方の普段見ることができない救出技術は素晴らしくて、とても感動しました。
これを機に、クルマを運転するなら日頃から教訓にしておくべきことを、お話したいと思います。

事故は突然起こることが多いので、頭の片隅にでも覚えておいてくださいね。
この記事を読んだら分かること!
- 縁石乗り上げ・タイヤパンク時の対処法
- タイヤの空気圧・スペアタイヤの空気圧
- パンクしたタイヤを交換する場合の費用
- いざというときの活躍グッズ

あまり難しく考えずに、さらっと見ていきましょう!
緊急時の対処法|縁石乗り上げ・タイヤパンク

こんな状況になった場合、まずどうなると思いますか?
人が集まってくるんです。
「大丈夫ですか?」って、親切心で次から次に・・・。
余計に心拍数が上がってきます。
私の父が運転するクルマで起こったことなのですが、一瞬の出来事だったそうです。
間口の広い駐車場入り口で、前方右側からクルマが横切ってきたので慌ててハンドルを切ったら、縁石に乗り上げてしまったそうです。

一瞬でくるっと、はまり込んでしまった感じでね。
そこら付近にいた人が集まってきて、一緒にクルマを動かそうと尽力してくれたそうなんですが、全く歯が立たなかったみたいです。

色々な人が声を掛けてくれたんだけど、どうしたらいいのかパニックになっちゃってね。JAFに連絡するようにって、言われるままに電話してたんだけど…。
誰にも怪我はなくてよかったのですが、突然の出来事にどうしていいのかわからなくて困ってしまったようです。
1-1.ロードサービスを利用する|自動車保険(任意保険)に連絡

自力ではどうにもならないときは、すぐにロードサービスを利用します。
怪我をした人がいる場合は、人命救助や救急車・警察を呼びます。
はじめての経験の時は、自分がロードサービスを利用するという感覚がないので、とりあえずJAFに連絡するものだと思っている人もいるかもしれません。

JAFに連絡するのは、最終手段です!
まずは、あなたが契約している自動車保険(任意保険)会社に無料のロードサービスが付帯されていますので、そこに問い合わせしましょう。
会員でない場合は有料での対応も出来ますが、実費になります。
無料でできるロードサービスを利用しないと、何のための自動車保険なのかわかりませんよね。
\ まずは任意保険の契約をした自動車会社に電話をしましょう /
自動車保険(任意保険)のロードサービス
- 契約しているクルマ(マイカー)に対して、トラブルに対応
- 等級など関係なく、応急処置をしてくれる基本のサービス
- バッテリー上がり、オーバーヒート、タイヤパンク、鍵の閉じ込み・紛失、ガス欠など
- 翌年の保険料に影響なし
JAFは会員制なので、入会金+年会費を払わなければなりません。
\ JAFは最終手段 /
JAFのロードサービス
- 会員制で、人に対してかかる保険(マイカー以外もレンタカーやバイクなど対応可)
- 入会金2000円+年会費4000円
- 会員でなくても有料対応できるが、会員が優先の場合も
- 24時間・365⽇、全国どこへでも対応

こういう時は気が動転するので、冷静に対応できる人に助けてもらうのが一番です。
一緒にいた母が既にJAFと連絡を通じていたのですが、私が断って自動車保険会社のロードサービスの手配をしました。
現場にレッカー車が到着したのは、連絡して30分後くらいです。
それまで既に2時間くらい経過していたので、対応が前後したりすると時間を浪費してしまいます。
ロードサービスの隊員2名が到着してから、最初に「念書」を書きました。
念書とは
『 事故または故障の現場における作業で、車体などに損傷などを生じさせる可能性が予測される場合は、損傷などが生じても実施業者を免責することに同意する… 』
上記の内容を記された念書に、署名しました。
作業中に多少の傷が生じても、傷つけられたとか言って責任を問わないでくださいね、という内容です。
この状況では署名せざるを得ませんが、「できるだけ傷つけないようにします」と言って作業をしてくれました。

そもそも乗り上げた時点で、傷ついてしまっていました。
1-2.縁石乗り上げの対処法
縁石に乗り上げた場合、衝撃でタイヤがパンクすることがあります。
この時も、前輪・左タイヤがパンクしていました。

縁石が思った以上に高くて、この状態からどうやってクルマを救出させるのだろうと、不安と期待が入り混じっていました。
救出はかなり苦戦してしまって、かかった時間はおよそ40分くらいだったと思います。
後半頃になると道具が足りないこともあって、救出は無理かもしれないので応援を呼ぶ手配までしていました。
私はそばで一部始終をみていたのですが、最終的には無事に救出していただき、本当に素晴らしいレスキュー技術でした。
思わず歓声を上げて、みんなで喜びました。
その救出内容は、こんな感じでした。
縁石乗り上げからの救出法
STEP 1 スペアタイヤに交換
乗り上げた前輪タイヤがパンクしていたので、タイヤをスペアタイヤに交換します。
使用するスペアタイヤは使う機会がないため、空気が入っていないことが多いです。(不安定になります)
➡いざというときのために、数年ごとに点検して空気を入れておく必要があります。
スペアタイヤは工具と一緒に、トランクの中に入っています。

こういう時のために、タイヤの空気入れを常に備えておくと助かります。
\ クルマのバッテリーで動くので簡単早い!/
タイヤ交換はあっという間に完了!です。
STEP 2 道具を使う
乗り上げたクルマをどうやって動かすのか?
使った道具は、油圧ジャッキと長板・車止めといった最低限の道具しかありませんでした。
油圧ジャッキ

油圧ジャッキは、重い車体をかんたんに持ち上げることができる便利な道具です。
縁石の段差が高いので、段差プレート・スロープなどがあるといいのですが、木の長板を代用していました。
STEP 3 車体を持ち上げて少しづつ方向転換
指示する隊長とハンドル操縦をするドライバーの2人で、連携して作業していました。
まず油圧ジャッキで車体を持ち上げ、乗り上げた前輪部分に長板を敷きます。(車止めも利用)
長板の上にタイヤを乗せて、小刻みに後退したりハンドルを切ったりして微調整しています。
後輪は地面についた状態なのでバックできるのですが、段差が高いことと車体が奥に入り込んでしまっていたことが脱出を困難にしていました。
無理をして脱出させると、車体が転倒する恐れがあります。

この工程でかなりの時間を要しました。
何度も何度も切り返しの作業を繰り返して、少しづつ車体を道路側にずらしていったことが大きなポイントだったと思いました。
簡単そうに見えますが、この技術は奥が深いです。
STEP 4 前輪左タイヤを後退させながら、縁石に乗り上げる
20cmくらいの高さがある縁石に板を固定して敷き、前輪左タイヤ(スペアタイヤに履き替え済)を後退しながら乗り上げようとするけど何度も失敗してしまいました。
➡スペアタイヤは通常のタイヤより細く空気圧が低すぎて、板の上の軌道にうまく乗らず、苦戦を強いられました。
ここを通過できず、何度も試行錯誤していました。
やっと前輪の左タイヤが縁石上に乗ることができると、もうゴール寸前です。
STEP 5 前輪左タイヤを地面に着地させる
縁石上に乗った前輪左タイヤを地面に後退させて着地するには、縁石が高すぎます。
➡無理に移動させてしまうと、車体が歪んだり傷つく可能性が高いです。
そこで、パンクしてしまった廃タイヤを敷いて使うことにしました。
事故現場では、使えるものは何でも利用するしかありません。

取り外したばかりのパンクした廃タイヤのホイール部が硬いのを利用して、高低差を解消する役目を果たします。
このタイヤの上に長板を敷いて、通路を作ります。

STEP 6 脱出成功!
何度も小刻みに軌道修正を繰り返しながら後退し、やっと前輪左タイヤが道路に着地しました。
全般的にとても丁寧で、安心できる作業内容でした。
油圧ジャッキ
油圧ジャッキは車体の下に長板を挟むときに、かんたんに車体を持ち上げることができるので大活躍でした。
緊急時には、とても役立つアイテムですね。
段差プレート・スロープ
無理に段差を通過しようとすると、衝撃が大きくて車体を傷つけたりタイヤパンクの原因になったりします。
段差の緩衝には、段差プレートを使うとスムーズです。

いろいろありすぎて実況をうまく伝えきれず、申し訳ないのです・・・
限りある道具しかなかったので、運転席で微妙な操作・ハンドル捌きをする人と、指示する隊長とのコンビネーションで、クルマは無傷で救出できました。
車体が縁石に乗り上げただけの状態ならよかったものの、勢いでその後に前輪左タイヤだけ落ちて、縁石の角にはまり込んでしまったので、本当に難しい救出作業だったと思います。
素人での救出は、到底無理だと思いました。
熟練した技術を駆使する現場に立ち会えたことは、本当に貴重で感動しました。

一時はどうなることかと心配したけど、ほっとしたよ。
帰路の走行
この後、スペアタイヤを履いて走行しましたが空気圧が激減していて、走行が不安定でした。
スピードもあまり出せないので、すぐ近くのガソリンスタンドに直行して空気を入れました。
スペアタイヤの空気圧がないと、走行が不安定でまっすぐに走行することが難しくなります。 ➡【緊急】ガソリンスタンドへ直行!

スペアタイヤの空気圧って、いくらか知っていますか?
1-3.タイヤパンクの対処法

タイヤがパンクしてしまったときの対処法をかんたんに説明します。
Step① スペア(予備)タイヤに交換する
➡クルマにスペアタイヤが積んである場合は、工具も一緒に装備されていると思います。
タイヤの交換方法は探せばいくらでも見つかりますので、ここでは割愛します。➜タイヤ交換
Step② 最寄りのガソリンスタンドで、空気圧を確保する
➡スペアタイヤの空気圧は、通常タイヤの約2倍です。指定空気圧は420kPa(4.2kgf/cm2)
普段の空気圧とは異なるので、知識として2倍と覚えておきましょう。
Step③ 早めに標準タイヤに交換する
スペアタイヤは他のタイヤと比べて径が小さくなるため、まっすぐ走行しているつもりでも微妙に斜め走行になってしまいます。
走行していると気持ちが悪くなるので、スピードを緩めて走行し、なるべく早めに新しい標準タイヤに交換しておきます。
タイヤのホイールの変形
ロードサービスの作業後に注意を受けたのですが、タイヤのホイール(フレーム)が少し変形していました。

変形したホイールを使うと、空気が抜けやすくなったりハンドル操作がぶれたりするそうです。
歪みは小さいのですが、念のために修理するか、中古品を探して購入するかを勧められました。
今回は、中古品で安いホイールがヤフオクで見つかったので、購入することにしました。

クルマの中古部品は、ヤフオクで探すと意外と見つかります。
タイヤ(ゴム)は新品をアマゾンで購入しました。
整備工場に、自分で購入したタイヤとホイールを持ち込んで、取り付けてもらうことにしました。
縁石に乗り上げた場合、車体の歪みが生じて車検時のサイドスリップ検査に引っ掛かることがあるようです。
乗り上げた衝撃で足廻りに損傷がないかの点検も、同時にお願いしました。
タイヤ1本分の費用
整備工場に依頼した内容(1本分)
- 新品タイヤ(ゴム)持ち込み:8,320円(アマゾンで購入)
- 中古ホイール 持ち込み:4,330円(ヤフオクで購入)
- タイヤ取付け 2,000円
- ホイールバランス 800円
- エアーバルブ 300円
- 廃タイヤ処分 1,000円
- 取付 500円
- 消費税 460円
合計: 17,710円
ロードサービスの費用は無料でしたので、タイヤ1本分の費用だけで済みました。
クルマの整備の節約方法
ディーラーや整備工場で整備をする場合、意外と費用がかかってしまいます。
クルマの消耗品などを交換する場合、工賃だけで取り付けを行ってくれるショップを利用するとかなり節約できます。
私がいつも利用しているのはタイヤの専門店ですが、エンジンオイルやタイヤ周りの消耗品の交換を、材料持ち込みでもお手頃価格で行ってくれます。
自分で選んだもの(=材料)を使いたいという人にも、おすすめですね。
全国店舗 COCKPIT(コックピット)(お問い合わせ必須)
1-4.タイヤ空気入れの使い方
ガソリンスタンドで、タイヤの空気を入れてみる

ガソリンスタンドには、無料で使える空気入れが備え付けてあります。

クルマの空気の入れ方、わかりますか?

やったことはあるんですけど、ちゃんと空気が入ったのかわからなくて・・・

クルマのタイヤは、適した空気圧があるので適当に入れるのはダメなんです。
簡単なので、覚えておいてください。
タイヤの規定空気圧
運転席のドアを開けて、ボディ側に規定表のシールが貼られています。
- 推奨されている空気圧『kPaかkgf/cm2』が、前輪・後輪ともに記載されています。
単位表記が異なる測定器であったとしても、なんとなくわかると思います。
➜ 例: 前輪220kPa(2.2kgf/cm2), 後輪230kPa(2.3kgf/cm2)
クルマのタイヤ空気の入れ方
STEP 1 自分のクルマの「規定空気圧」を確認する
運転席側のドア付近に、シールが貼ってあります。

STEP 2 タイヤのバルブキャップを外す

バルブキャップは無くしやすいので、取り外したらポケットなどに入れておいたほうが無難です。
転がって、ちょっとした穴に入り込んでしまいます。
STEP 3 測定器の先端を平行に押し当てる

測定器の種類にもよりますが、据え置きタイプのものの場合は、最初に自分のクルマの「規定空気圧」にメーター針をセットします。
先端部を穴に差し込んだら、平行にグッと押し当てて下さい。
そうすると「シューシュー」と空気が入っていく音が聞こえます。
押したり引いたりせずに、グッと「長押し」で押し付け続けてください。
規定空気圧になると、空気が入っていく音がしなくなります。
STEP 4 規定数値より少し多めに入れる
ピッタリの空気圧を入れることは難しいと思うので、規定数値より少し多めに入れておきます。
STEP 5 バルブキャップを閉める
忘れずに、バルブキャップを閉めておきましょう。
1-5.日常点検と役立つおすすめグッズ
タイヤ空気圧センサー
\ 空気圧の監視センサー/
空気入れ➜高圧フットポンプ

\ どこでも気軽に使えます /
\ クルマのバッテリー電源で動くので簡単早い!/
油圧ジャッキ

段差プレート・スロープ
△三角停止表示板
バッテリー|バッテリーチャージ
LUFT ジャンプスターター 13600mAh
\ 楽天市場で最も売れているジャンプスターター /

まとめ|緊急時の対処法と日常点検


安心してクルマに乗るために、知っておくべき緊急時の対処法をご紹介しました。
自分ではどうにもできないと思ったら、すぐに自動車保険会社に電話しましょう。
免許証や車の中に、保険会社の「証券番号」と「電話番号」のメモを入れておくのも大事です。
そして、日頃からタイヤの空気圧にも気をつけておく癖をつけてください。
1カ月に1回くらいのタイヤ点検を心がけて、安全走行するようにしてくださいね。

では、今回のまとめです。
- クルマのロードサービスは、加入している任意保険の自動車保険会社へ電話する。➡証券番号と電話番号のメモを免許証と一緒に持っておこう。
- スペアタイヤの空気圧は、約2倍必要。 ➡数年ごとに空気圧の点検をしておこう。
- 1か月に1回くらい、タイヤの空気圧点検を行おう。
- 緊急時にあると役立つグッズを、常備しておこう。
【点検整備の関連記事】

このブログでは、ユーザー車検にチャレンジするための解説を詳しくしています。
初心者、女性、年齢問わず、誰でも始められます!